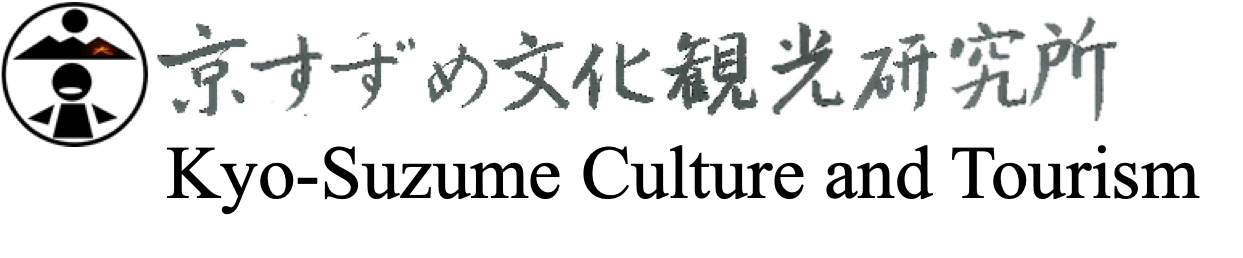京都の引力21 始末と掃除の心
土居好江
 |
 |
「しまつ」と言うとわかりにくいのですが、「始末」と漢字で書くとわかりますが、始まりと終わりのことですね。京都で言う始末とは片付けると言う意味よりも慎ましく浪費しないことで、倹約にも通じます。「もったいない」とい言葉は世界共通語になっています。英語にも無い表現と言われています。
始末とは使い始めと使い終わり、例えば昔は浴衣が古くなるとタオル代わりにして使い、更にオムツとして使い、紐として使い、最後に雑巾にして使ったようです。このように無駄なく使いきることが始末だったようです。現在なら、リメイクして着るとか、メルカリで売るとかでしょうか。使い捨てるだけでなく、使い切ることが始末の極意です。
京都には、門掃きとか、打ち水と言う文化があります。掃除も、掃き清めるという姿勢の掃除です。日本には汚れたから掃除するのではなく、汚れないように掃除するというスタンスがありました。これは祓いの文化です。場を浄め整え、自らの心身も浄め整えることができるということです。
かつて、掃除の神様と呼ばれた鍵山秀三郎先生が見えない心を掃除する為に、目に見える掃除をして片付けると、心が整うと申されました。断捨離ブームは、大量生産、
大量消費時代を経て、モノに溢れかえった身の回りを整理することで、不要なものを捨て去り、モノへの執着を捨てて快適に暮らすことです。
私もモノが多くなり、現在断捨離中です。ネガティブなエネルギーを排除して、ポディティブなエネルギーを輝かせるための整理整頓と理解しています。
かつて、日本電産の永守重信氏が「6S」と言う言葉を使って、整理、整頓、清潔、清掃、躾、作法が大事と申されていました。永守氏のセミナーを何回も拝聴して、いつも仰っていたことは、「業績が悪い会社は整理整頓ができていない。だから、掃除と整理整頓をすると、それだけで業績があがった会社が何社もあった」と。
心の様子が部屋の様子と言うことでしょうか。場を浄め整えることは、自らの心身を浄め整えることに通じると、京都の名所にお伺いすると掃き清められている清々しさを体感します。目に見えない想いが掃除という行いを通して、清々しさを感じる方は多いと思います。こういう想いで、我が家を断捨離中です。
以上