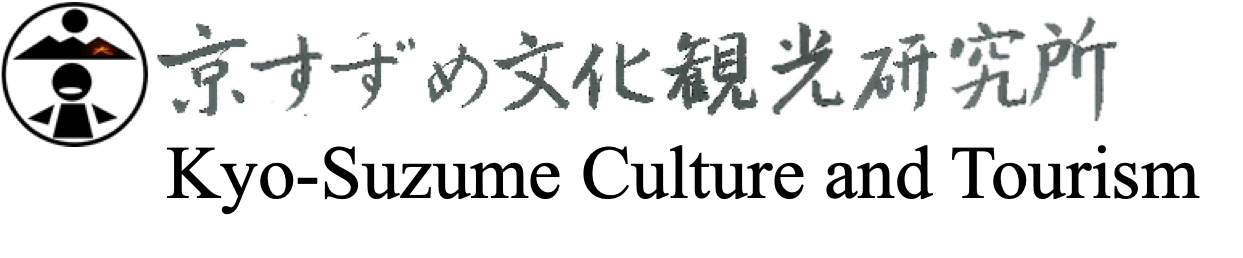京都の引力19 京言葉、心を整える
土居好江

京都生まれで京都育ちの私には、自分自身が京言葉を話しているという自覚がありませんでした。標準語を話していると思い込んでいたのです。ところが、首都圏で講演などをさせて頂く時に、「今日は京都弁が聞けてうれしい」と必ず申されるのです。
ゆっくりと、イントネーションも京都言葉らしく、「○○したはる」とか路地を「ろぉーじ」「ありがとう」と「ありがとぉ」というように、京言葉は母音を伸ばして話します。
私はよく老舗に、お電話することが多く、電話を切る時は、必ず最後に「おおきに」と申されます。また、嬉しさを伝える時は「おおきに、うれしおす」と申されます。こちらまで、嬉しくなります。心地良いリズムではんなりとやさしく申される老舗の女将さん、こういう方とお話していると、「あぁ京都にいるんだなぁ」と思うのです。ゆっくりとお話されるテンポは京都のテンポといえるでしょうか。
言葉の世界とは言え、ストレートにモノ申す時も柔らかくなります。長い都の歴史で権力者が代わっても、敵味方が変わることがあっても、柔軟に対応できる予防線が、京言葉の曖昧さを生んだのかもしれません。
有名な話で夏目漱石が祇園の舞妓さんを誘った時に「へぃー。おおきに」との返事をOKと思い込み、約束の日時に現れない舞妓に電話をしても「へぇー、おおきに」と言うばかり。「おおきにとはyesともnoともとれる状況判断を含む言葉です。高度な会話は時には全く反対の意味になるのが、京言葉なのです。
京都では感覚言語というか、「ほっこり」とか「はんなり」という感覚的な言語が発達していると思うのは私だけでしょうか。大阪弁で「ぼちぼち」と言う言葉があります。「儲かってますか」「へぃー。ぼちぼち」と。京言葉でいうと「儲かってますか」「へぃ、おおきに、ぼちぼちやわぁー」となります。
何かお願いする時は「よろしゅー、おたの申します」というと、相手の返事を待つまでもなく、お願いしたことになるのが京言葉です。苦い体験をしたことがあるのです。こちらはお返事をしていないのに、OKという認識をされたのでした。
京都を形容する代表的な言葉は「山紫水明」。江戸時代の頼山陽が丸太町の書斎山紫水明処の鴨川から東を見て山紫水明と言う言葉をつくりました。まさに、この山が紫に染まるというのは、夕焼けのできる時刻のことを指しています。現在では形容詞として使われていますが、頼山陽は手紙に「山紫水明の頃におこしください」という手紙を書いたのがはじまりです。
京都には、美しい言葉が沢山遺されています。時刻を表す言葉が「山紫水明」という今や京都を形容する代名詞を作り、目に浮かぶ情景が言葉になっています。こういう心を大切にする京都人の文化度の高さに、憧れの京都が出来上がったのかもしれません。
「京都十代、東京三代、大阪一代」と言われるように、京都人と認められるためには何代にもわたって暮らす必要があるようですが、このまったりした京言葉を残していきたいと思うのは、歳のせいでしょうか。
以上