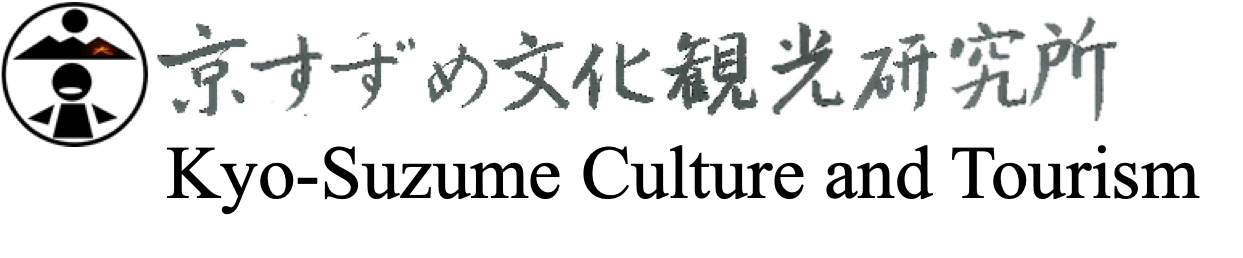京都の引力12 老舗の無形資産1
土居好江
 |
 |
 |
あぶり餅一和 平野屋 入山豆腐
京都には587年創業の池坊華道会、771年創業の源田紙業、885年創業の田中伊雅仏具店、そして、1000年創業のあぶり餅一和の老舗があります。
飛鳥時代創業の池坊華道会は仏教伝来と時を同じくして、仏に花を供えることが一般化して、平安時代の鳥獣戯画に中にも仏花と数珠が描かれていて、思わず微笑みました。ウサギや蛙が数珠をもっています。また、法要の場面では、猿の僧侶が数珠を手に花をお供えしています。現在でも同じ光景が人間の手によってなされていることに、歴史の長さを感じます。
源田紙業の源田社長には、京すずめ学校「京都木気物語」で水引のご講演を賜りました。あぶり餅一和のご当主・長谷川検一氏はおくどさん未来衆の代表としてご尽力を賜っております。一和のあぶり餅は創業当時から、製法もほとんど一緒で、同じ場所で同じあぶり餅の製造販売の茶店を1025年間営んでおられます。お餅を黄な粉でまぶして炙ります。千年間、同じ方法です。京すずめ学校でも2回、講座を開催させて頂き、おくどさんサミットも開催させて頂きました。現存する世界最古の茶店(カフェ)です。
愛宕神社の一の鳥居脇の平野屋では、400年間、おくどさんでご飯を炊いておられます。実際に木や藁から火を熾し、手間暇かけてご飯を炊いておられます。入山豆腐店では大豆をおくどさんで200年間炊き続けておられます。ガス。電気の時代に何故、おくどさんで炊き続けるのか、それは美味しいからです。便利さよりも手間暇かけたご飯や豆腐、小豆が美味しいからです。これは、また、次章で述べることにしますが、食べ比べすれば判ります。香りや煮炊きの具合が異なるのです。
最近、思うことは、おくどさんという伝統的価値観に、パラダイムシフトの架け橋となる価値が詰まっていると痛感するのです。便利さだけが価値ではなく、人間の五感、火のぱちぱちという音や、匂い、火のゆらぎを見ていると、脳波が活性化されるような感覚を覚えます。
また、京文化の奥深さには驚きます。京都では火種を重要視します。新年を迎える火種を頂く八坂神社のをけら参りでは、をけら灯籠から吉兆縄にをけら火を移し火が消えないように自宅に持ち帰ります。新年には火や水を新しくして迎える風習があるのです。井戸から汲み上げた若水で雑煮をつくることが一般的でした。
御所がある京都では、長年天皇家で誕生するお子様の産湯は川端道喜のおくどさんの火で沸かされました。明治天皇ご誕生の折の産湯の火種も、川端道喜のおくどさんの火で中山邸の井戸水を沸かされています。川端道喜が宮廷に納めていた品の中には灰もありました。
仁孝天皇崩御の折には計53俵の灰を納めておられています。川端道喜では火の清さを守り通すために、おくどさんで薪や柴以外のもの、例えば紙屑なども燃やさないことで、火の清さを守っていたそうです。この習慣は明治維新まで続きました。
眼には見えない火の神聖さにも心配りをした京文化の奥深さに驚くばかりです。この奥深さを掘り起こしことで、新しい価値を知るパラダイムシフトの架け橋となることが、できるのではないかと私は考えています。
ヨーロッパの歴史を見ても、オーストリアのレストラン・シュティフツケラー・ザンクト・ペーターが803年、パリ造幣局が864年創業、イギリスの王立造幣局が886年と800年代の創立です。はやり、生存に最も必要な、レストランが世界でも創業が古いですね。
世界には1300年以前に創業され、現在も営業している企業が世界で50社あります。そのうち24社が日本にあります。200年以上続いている企業が世界で5586社ありますが、そのうち3146社が日本の企業です。日本企業の息の長い取り組みは世界的にも知られています。この日本企業の強みを更に深堀していく予定です。
創業からの経営哲学や、技術、商品への愛着、文化を受け継ぎ、次世代へ繋ぐ架け橋の役割を京都の企業が担っていると感じています。
以上