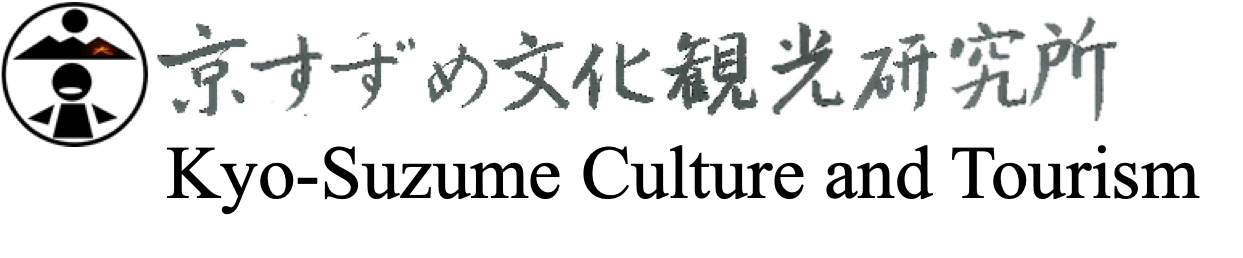京都の引力 14 陶器と漬物Ⅰ
 2025年8月8日撮影 2025年8月8日撮影若宮八幡宮境内 五條若宮陶器祭・大祭 |
 2020年1月30日撮影八隅農園すぐき小屋 2020年1月30日撮影八隅農園すぐき小屋 |
 |
土居好江
古くから言われていることに、陶器が発達した場所の土で育った野菜は、美味しく味がよくて柔らかいと。京都は琵琶湖の水と地下水が豊富で、京野菜がブランドとして知られています。陶器も京焼、清水焼等、ブランドとして知られています。土と水、しかもそれを活かした京文化の歴史が共通項にあります。
8月8日、京都東山五条坂にある若宮八幡宮の陶器祭・大祭にお招きを受け、参列して参りました。雅楽が演奏される中、厳かに神事は執り行われ、その後は太鼓の演奏で大いに盛り上がりました。
五條通りは陶器の販売店が屋台を出し、既存の店舗も値段は3割引き、半額等のサービスを提供して、年に1回の祭を盛り上げます。五條通は秀吉時代に現在の松原通を南に拡げて五條通りとしました。もともとの五條通は現在の松原通です。ですから、牛若丸と弁慶の争いも現在の狭い松原通が舞台だったのです。
現在は五条若宮陶器祭として、コロナ禍の中断から復活しました。京都の夏の風物詩が蘇って多くの方々が喜んでおられます。陶器祭のルーツは1920年(大正9年)、六道珍皇寺の8月7日から10日に行われる「精霊迎え六道まいり」の参拝する方々に、日頃は売れ残ったものを安売りする露店市のようなものが、陶器市が始まりでした。1954年(昭和29年)から若宮八幡宮の大祭となっています。現在では約400の出店があり全国でも最大規模の陶器祭となりました。
この地域は清水寺、祇園、京都国立博物館、六道珍皇寺が徒歩圏内にあり、清水焼発祥の地を楽しむことが出来ます。室町時代、宝徳期(1449~52)に音羽屋九郎右衛門(おとわやくろうえもん)が清閑寺(せいかんじ)、東山区清閑寺山ノ内町)の近くに開窯した音羽焼が清水焼のルーツであるといわれています。音羽焼は清閑寺の庇護を受け発展しましたが,慶長年間(1596~1615)末に阿弥陀ヶ峰の豊国廟に煙がかかるため,命により清水寺近辺へと窯を移転しました。江戸時代は清水寺から煙が立ち上る絵図がのこされています。
さて、肥沃な土で育てられた京野菜が漬物として、親しまれている歴史の長い紫葉漬けは、平安時代に大原に隠棲した建礼門院が、里人から差し入れた漬物を「紫葉漬け(しばづけ)」と名付けたと言い伝えられています。この「紫葉」とは赤紫蘇のことです。すぐき漬けや千枚漬けと並び、京都の三大漬物の一つに数えられています。
京都には千枚漬という漬物とは思えない、贅沢な漬物があります。長期保存用というよりは季節の聖護院かぶを季節のうちに食する贅沢品です。江戸時代末期、御所の料理人だった大藤藤三郎が考案して、店先で千枚漬けのかぶを薄くスライスしていたら、お客さん方から、「あれは千枚あるで」と言われ、千枚漬けと名づけられたという逸話が残っています。明治23年(1890年)に京都で開かれた全国博覧会で、全国名物番付けに入選するまでになり、千枚漬が知られるようになりました。
1300年前の奈良時代から貴族の間で食されていたすぐきの漬物は、京都の三大漬物の一つです。京都では江戸時代中期より上賀茂で栽培され、塩と職人の技で、すぐきの漬物がつくられる正真正銘の乳酸発酵の自然食品です。
市販の漬物はふつう漬物屋が作っていますが、すぐき漬けは作り方を代々引き継ぐ上賀茂の農家が作って卸しています。有り難いことに、私はこの三大漬物の工房や畑にお伺いして、ご当主様からいろいろなお話を賜りました。その漬物のルーツには考案した方が深い愛情を持っておられたことを痛感しました。 (次号へつづく)
以上