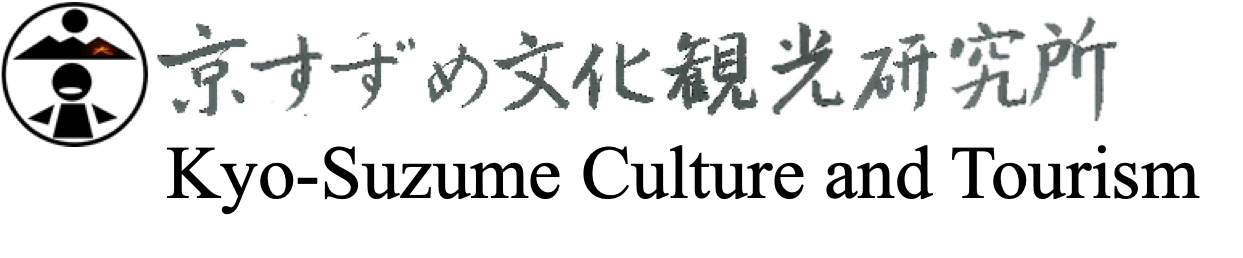京都の引力Ⅳ 寺子屋と維新後の番組小学校
土居好江

2025年5月20日撮影
京都慶応義塾跡の石碑
京都府庁正門入る東
京都は江戸時代から、寺子屋が数多くあり、幕末に京都府で寺子屋は566軒、私塾は34と全国の中でも群を抜いて多くありました。『日本教育資料』によると、全国に寺子屋が1万5千軒から2万軒ほどあったようです。
京都では、他の地域に比べて女性の師匠が多く、商人のために、夜間に寺子屋を開校したことも京都の特徴です。維新前から、教育への意欲は高く、京都の町ぐあげて取り組まれました。
その歴史を踏まえて、明治に入り、町の自治組織ごと番組小学校が建設されたのでした。その運営には小学校会社をつくり、運営から貸付、竃金の管理とうが、行われました。竃金とは竈の数によって寄付金が決められて、町組が小学校を支え教育の場だけでなく、警察の屯所や消防の機能もあり、いわば行政機関としても機能でしていました。
年々、寄付をする方も増え、その利息を生徒の授業料に当て、徴収を免除する学区もありました。教育に京都の未来を託す京都人の強い意志を感じます。また、特筆すべきことは小学生だけでなく、大人も曜日を決めて小学校に通い、世界情勢などを聴講して学んでいたのでした。
あまり知られていませんが、旧京都守護職邸内の京都中学校教場の一角を間借りした京都慶応義塾が明治7年(1874)2月開設されました。現在の京都府庁の場所です。わずか1年間の開校でしたが、学生を集めることが難しく閉鎖されたのです。京都府庁の正門西側の守衛室の東に石碑があります。
福沢諭吉は明治5年(1872年5月)に京都を訪れ、『京都学校之記』で、京都の教育制度を絶賛していました。京都には神社仏閣の総本山も多くあり、子弟の教育に熱心な京都で、全国から修行で滞在する方々が、行儀作法も知識も智恵も身に着けてきた長い歴史が、教育の分野でも活かされたのだと思います。
京都は伝統と歴史のまちですが、併せて先進的な取り組みも大胆に行われてきました。教育も他都市には類を見ない先進的な取り組みで、維新後の京都の活性化を試みました。
以上