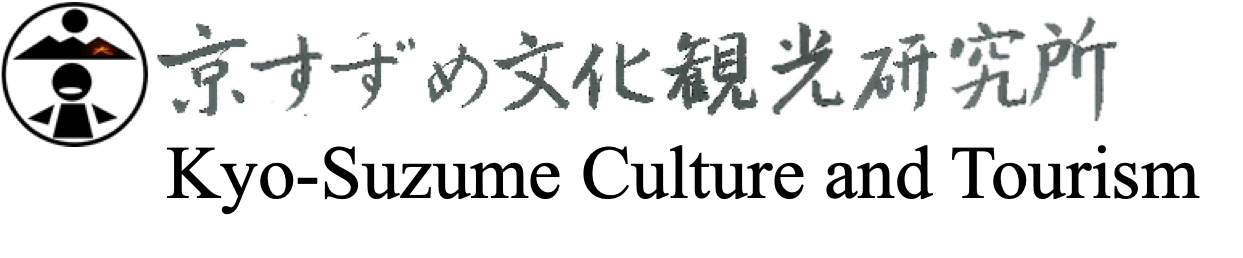和食のルーツを探る
土居好江

世界でブームになっている和食のルーツは、平安時代に遡ります。一汁三菜で、ご飯、味噌汁、おかず(お菜)と漬物の4つの基本が出来たのは平安時代末期と言われています。
水が豊かで、四季があり、山の幸、海の幸に恵まれ、湿気の多い日本でしかできない麹が旨味調味料となり、和食は発展して参りました。京都にも平安時代からの伝統が受け継がれて、行事食や祭のご馳走が発展していきました。
平安京が京都にできた3ヶ月前(794年7月)に都の東西市が建設され、七条坊門と七条大路に区切られて、朱雀大路を中心に左右対称に市が設置されたのです。月の前半15日までは東市、16日後半から西市で取り扱う商品も細かく決められていました。市は正午に開かれ、日没前の太鼓の合図で解散となります。
東西両市で販売されていた食品では索餅(さくべい、奈良時代に伝わった唐菓子の一種で素麺の祖。昔は京都にも素麺が作られていました)、油、海藻、菓子、干魚、生魚、米、塩、東市では麦、醤、海菜(※海藻)、西市では未噌(味噌)等が販売されていました。ここにある油とは灯油のことで寺社の多い都での需要が大きかったようで、食用油ではありません。
平安時代は野菜も魚介類も菜(な)と言い、おかずのことを意味していました。奈良時代にサカナは酒菜と書きました。野菜も魚も副食物は菜と呼んでいたようです。
当時は一日、二食の食事で、『おあん物語』(江戸前期の作品で、彦根の武士の家庭)では、朝夕二食で雑炊を食しており、山へ兄が鉄砲を撃ちに行く時だけ采飯を食すことが出来ました。(なめしは、刻んだ青菜を炊き込んだご飯で、さっと湯に通して塩を加えた混ぜご飯のこと)が食せたと記述されています。一日三食になったのは、江戸時代後半のことです。
日本最古の料理書ともいわれる『料理物語』(1643年)には油脂を使った調理法は紹介されていません。安土桃山時代に伝わった天ぷらは脂が高くて、庶民には遠い存在でした。長崎から関西に伝わり、江戸へ伝わり、ファーストフードとしての屋台の天ぷらが人気を得ました。
元来、和食は「煮炊き」「生」が基本でした。日本は綺麗な水が豊富で、魚介類も生で食したり、酢漬け、塩漬け、焼き物、つつみ焼き、蒸しもの等で頂きました。
大根おろし以外の野菜は煮るか漬物にして食し、醤油や味噌の発酵調味料と昆布、鰹節、煮干し等で味付けをしていました。戦後、女性に人気の野菜サラダは西洋野菜の人気を押し上げ、レタス、クレソン、ブロッコリー、セロリーが食されるようになりますが、近年のことです。
和食は、日本文化のエッセンスであり、自然の恵みに感謝し、四季折々の旬の野菜を頂く贅沢な食事です。毎日、感謝して「頂きます!」。
以上