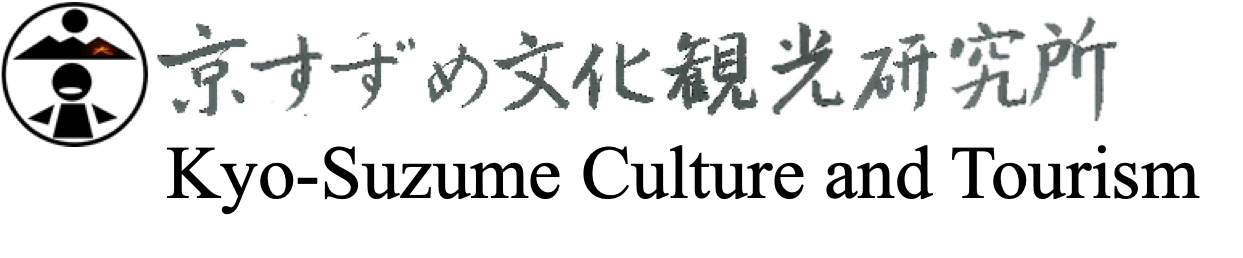京都の引力Ⅶ 夏の風物詩・七夕の意味
土居好江

2024年7月 北野天満宮
毎年7月7日は七夕です。もともと奈良時代に中国から伝わった行事で、旧暦の7月7日に行われていました。現在では7月に行われることが多くなりました。
1月1日
3月3日、
5月5日、
7月7日
9月9日
この奇数の数字は古代中国の陰陽五行説で奇数が「陽」の数とされ、縁起が良いとされています。
七夕をたなばたと詠むのは、いろんな説がありますが、年代をさかのぼって、大和言葉、縄文言葉とも言われている一説もあるようです。
江戸時代では、五節句(1月7日(人日じんじつ)・3月3日(上巳じようし・桃の節句)・5月5日(端午たんご・しょうぶの節句)・7月7日(七夕しちせき・たなばた)・9月9日(重陽ちようよう・菊の節句)の中で、重陽の節句が一番公的な行事としておこなわれていました。武家では、杯に菊の花を浸して酒を飲み、庶民は粟ご飯(あわごはん)を炊き邪気払いをして、長寿を願いました。
しかし、七夕の行事をはじめ、桃の節句、端午の節句と言われる子供にまつわる行事が根付いています。現在では子供たちが願いごとを短冊に書き、笹飾りをするのが七夕であると思われていますが、本来は恋愛の遊びでした。梶の葉はラブレターの象徴とされ、この梶の葉が活躍しました。
千何百年も受け継がれてきた恋物語が七夕の行事であり、恋の行事だったのです。七夕の起源は牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)を祀り、芸事の上達を祈る「乞巧奠」でした。宮中の儀式が民間に広がり、受け継がれてきました。
もともと「棚機(たなばた)」とは、古い日本の禊ぎの行事で、機織りの女性が着物を織って棚にそなえ、神様をお迎えして秋の豊作を祈る、穢れを払う禊の行事でした。
選ばれた女性は「棚機女(たなばたつめ)」と呼ばれ、川などの清らかな水辺にある機屋(はたや)にこもって神様のために心をこめて着物を織りました。そのときに使われたのが「棚機」(たなばた)という織り機です。
この伝説が仏教の伝来として、お盆前の禊(みそぎ)の行事と結びついて、現在に伝えられています。人々の心の中で息づいてきたものですが、現代では願いごとをする日というイメージが大きくなっています。本来は豊かでロマンチックな七夕の物語の日ですが、現在では、笹に願ごとを書いた短冊をつるす日です。
何故、笹につるすのか、笹には冬場でも青々としていることから生命力が高く、邪気を払うとされてきました。虫除けにも効果があり、竹は成長が早く、まっすぐ天に向かって伸びていくので、願い事を織姫、彦星に届けてくれると考えられていました。また虫などを除ける効果もあり、当時の稲作のときには笹を使って虫除けをしていたことや、天に向かってまっすぐ伸びる笹は願い事を空の織姫、彦星に届けてくれると考えられていたようです。
ここで、『新古今和歌集』から一首
七夕の門渡る舟の梶の葉にいく秋書きつ露のたまづさ(藤原俊成)
以上