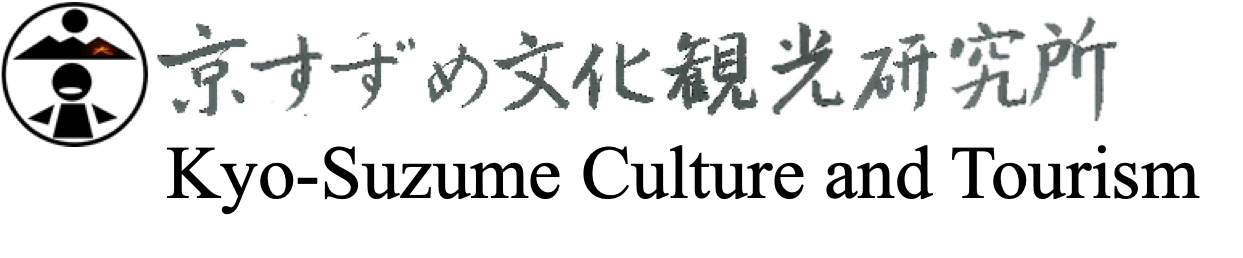ハイヒールのルーツと外反母趾Ⅱ 重要文化財のトイレと日本の隠れた歴史
土居好江
 東福寺の東司(重要文化財) |
 一休寺の東司(重要文化財) |
 日本最古の洋式トイレ新島嬢邸(京都市) |

阪神大震災直後、約2700基の仮設トイレ(神戸市) |
 正月のトイレの鏡餅十二の餅 12ヶ月お世話になるので12個 2012年1月1日撮影 |
京すずめ創立当初、その中で「京都至宝のトイレを巡る」というフィールドワークを行いました。この時は重要文化財のトイレを廻り、畳敷きの洋式トイレ、日本最古の洋式トイレなどをフィールドワーク致しました。こういうフィールドワークを何回も開催していました。
当時、大学の学長さんや芸術家、絵付けトイレ作家など、面白いメンバーで廻りました。歴史的なトイレは視察だけでなく、文化観光でも楽しめます。特に食事と排泄の関係は切り離せないものとして、人間の存在に関わるものです。
一休寺は20年ほど前は実際に用を足すことができましたが、現在では見学するだけです。料亭の宮家の畳敷きの洋式トイレや絵付けトイレ等、あちらこちらを巡っては楽しんだことを思い出します。
ヨーロッパのハイヒールが糞尿よけから生まれたことは、先に述べましたが、。中世のパリは路上に放尿する習慣があり、汚物で一杯になった道を歩く足元は長靴が最適で、汚物対策用の底の厚い靴が流行り、これがハイヒールのルーツとなりましたが、人間の考えることは同じで、高下駄のルーツも糞除けです。ちなみに,宮殿がパリからベルサイユに移ったのは、まちが不潔だったからだとも言われてます。
日本ではまちが綺麗で、田畑への循環もあり、この習慣は昭和の時代まで続いていました。 わが国のトイレの普及は鎌倉時代と考えられ、糞尿を肥料とすることによって農業生産が増えたことから、田畑に戻す自然循環の生態系をつくっていました。田畑に戻すまで糞尿は溜めておく必要があり、 室町時代には糞尿が金銭で取引され、その獲得は農家にとって死活問題でもありました。
歌舞伎発祥の阿国(おくに)が北野社(北野天満宮)で歌舞伎踊りを初めて行った1603年に,境内の右近の馬場辺りで、布を張り巡らせて公衆トイレが作られたのが、公衆トイレの始まりと云われています。北野社界隈は猿楽,曲舞などの興行が行われ、広場的な役割を果たし、貴賎衆庶の参詣で賑わいました。
明治時代に入り、自由民権運動の波に乗り一般にも新聞が普及し、その結果、新聞を小さく切ったものが、元祖トイレットペーパーとして使用されました。落とし紙として使われはじめのです。今まで葉っぱや葺が使われていたことを思えば、まさに「トイレの文明開化」が明治維新ではじまったのです。社会問題とトイレの関係も蜜であります。
最近では大阪万博のトイレ問題で、日本のセンスの良い気高いトイレ感覚が、思わぬところで認識されました。歴史に埋もれていた視点を拾いながら見る歴史も面白いものです。
以上