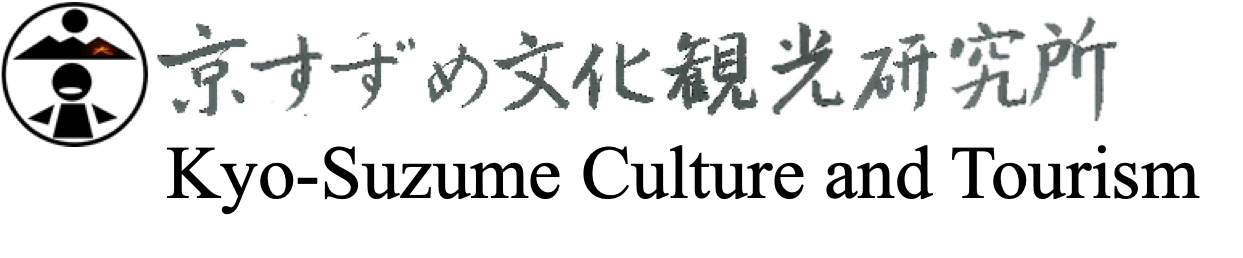錦市場と高下駄とハイヒール1
土居好江
 2022年1月28日撮影 人影のない錦市場 |
 2025年4月14日撮影 大混雑の錦市場 |
 |
 |
お茶室のようなトイレ
 小学校の校庭に石灰を撒いて埋めた様子 |
 クレゾール液 |
1995年1月神戸市 阪神淡路大震災の避難者調査より
土曜日の夕方に錦市場へ行くと、多くの海外の観光客と出会います。「ここはどこ?」と思うほど、ほとんどが海外からのお客様。日本人を見つけることが難しいほどです。
錦市場へ行くと必ずご紹介する歴史があります。一つは清涼な井戸水が市場となったという歴史、もうひとつは大通りから一筋入った路地は、トイレ化するという歴史です。世界各地の共通の法則らしいのです。
30年ぐらい前にパリ大学の教授でトイレ史の世界的権威のロジェ・アンリ・ゲラン博士の講義を拝聴したことがあります。日本人の知らないパリの歴史など、興味深いものでした。
中世のパリでは2階の窓から、おまるに溜まったお小水を投げ捨てていました。大きい方は道に捨てていた時期があり、それで、道路の糞除け靴の厚底靴ができたのです。進化したのがハイヒールです。ナポレオンが公衆トイレを整備したとお聞きしました。まちづくりに尽力されたというのを鮮烈に覚えております。
京都では路上や溝で用を足すのが普通だった江戸時代に、町の辻々に桶で作られた公共トイレが設けられて文化観光都市としての万全の備えがあり、美しいまちづくりを江戸時代から目指していたようです。
日本でもトイレの糞除けに高下駄ができ、それが、公衆的なトイレのあった錦市場のトイレにもあったとされています。錦市場はもともと「具足小路」と呼ばれていたのは、具足を販売するお店が多かったことにも起因しますが、大通りの一筋入った路地のお決 まりの運命でしょうか。天喜二(1054)年に後冷泉天皇の宣旨により、具足小路を錦小路と改名されました。
高下駄もハイヒールも、現在ではおしゃれで先の尖ったハイヒールを履いた中世の貴婦人は、ほぼ全員が外反母趾だったと、遺骨が物語っています。実用的からおしゃれ靴に進化した過程で、身体には良くないものデザインになったと思われます。
世界最古のトイレの発見とは、BC2200年ごろシュメールのウラという廃墟からレンガを積み上げて造った腰かけとアスファルトを塗った排水管が発見されたのが、世界最古のトイレらしいのです。
そもそも人間が決まった場所で用を足すようになったのは、実は縄文時代で、今から4000年~6000年前、川に杭を打ち込んで厠として遺構が福井県見方町で発見され、これが厠の跡といわれています。
パリの中世のお城を訪問した時、おまるの穴あき椅子の実物を拝見しました。
日本では6世紀におまるが渡来して、平安貴族は漆で塗った重箱のようなものに用をたしました。お姫様を慕う男が手に入れたと言うお話では、それにもお香が振りかけてあって、更に想いが深まったそうです。
京野菜は公家の排泄物と水と芳醇な気候と土地から発祥したとも言われています。室町時代には洛中洛外図に共同トイレが描かれています。
江戸時代に書かれた『東海道中膝栗毛』では弥次さん、喜多さんが清水詣でで三条を歩いているとき、「大根小便しよしよ.」と、大声で小便たごを担いだ小便取りの男が路地裏で大根3本と小便が物々交換される様子が描かれています。
しかし、申し出た男二人の小便の出が悪く喧嘩になり、喜多さんの小便を足して大根2本に値切ったところ、3本と交換されたという物語が描かれています。
神戸の大震災の折、震災後1週間後の避難所の調査で、トイレの重要性を痛感しました。
(次号へつづく)