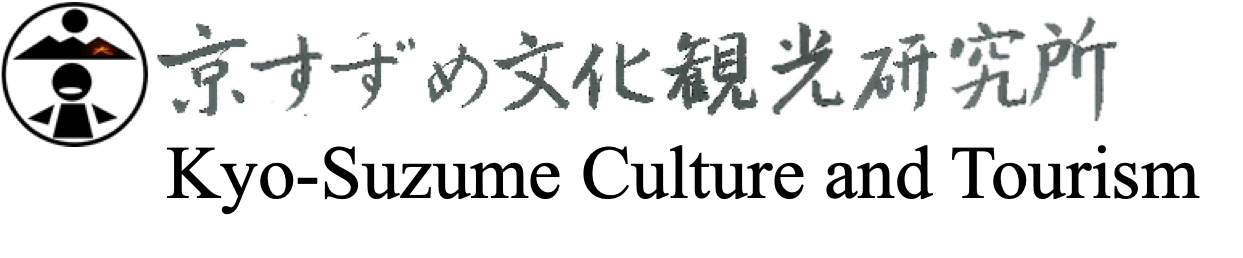京都の引力18 京都御所 鬼門と天門
土居好江

天皇は毎朝、起床されると体を清め、そこで「祈り」の儀式をされました。京都から伊勢神宮の方角が東南の隅にあたるので、内裏の「清涼殿」(せいりょうでん)天皇のお住まい)の東南の隅に、「石灰の壇(いしばいのだん)」が設けられます 「石灰の壇」というのは、板敷きと同じ高さに、床下の土築きあげ、その上をしっくい(石灰)で塗り固めた場所のことです。
天皇のルーツである天照大神が伊勢に祀られているので、東南の隅だったのです。太古から続く祈りは歴代の天皇に受け継がれてきました。每朝の「祈り」は、第五十九代の宇多天皇(867~931年)の時代には儀式化されていたようです。
都が平安であるように祈り続けた歴代の天皇の祈りの記憶が、京都御苑の敷地に足を踏み入れると、私は感じられるのです。
中国・宋に時代((960年~1279年)に鬼門の方向(北東)から鬼が入るので、鬼門封じに鐘をついて 丑寅の間を封じてきました。丑と虎を月に直すと12月と1月の間です。大晦日に邪気が入るので、鐘を使って邪気をはらってきました。
除夜の鐘も、一年の締め括りに、古いものを捨てて新しいものを迎える習慣です。初詣も、古くから天皇が新しい年を迎えるのに東天に昇る太陽の光を拝むという習慣がルーツです。
元旦には天地四方拝といって、国民の健康と国の繁栄を祈る行事を天皇は2600年続けていますが、元々の意味は初日の出を拝むということが、段々神社に詣でる歴史となってきたのです。心も身体も洗うように脱皮して新しい年を迎えることが、本来の初詣の意味です。
ちなみに桓武天皇も鬼門封じに比叡山に延暦寺を建てました。その延暦寺からまっすぐに降りると御所にたどり着くと言われたものです。裏鬼門は反対の南に石清水八幡宮が建てられたのです。
鬼門に対して天門という考え方があります。力のある場所を更に強くする考え方で、京都の代表的なものに、大将軍八神社があります。平安京建都の折、桓武天皇は都の土地を更に強くする為に、天門の地に神社を配しました。
明治時代に天皇が東京へ行かれて人口が減少し、産業が衰退した時、明治28年に国内博覧会を岡崎で開催し、まちおこしをしようということで、現在の動物園の場所に記念の大極殿を再現しようと試みました。
しかし、方角が悪いと市民の反対運動がおこり、現在の平安神宮の場所に大極殿、青龍、白虎や応天門を造営し、パビリオンではなく桓武天皇等を祀る神社が創建されたのです。
この平安神宮は京都府民が資金を出し、知事が全国行脚して募金を集めて建設されました。地鎮祭の折には町内ごとに揃いのゆかたを着て、三日三晩踊り明かしたと伝えられています。さらに家路につくまでに事業所を見つけては踊り込みまでして、喜びを表したそうです。
以上