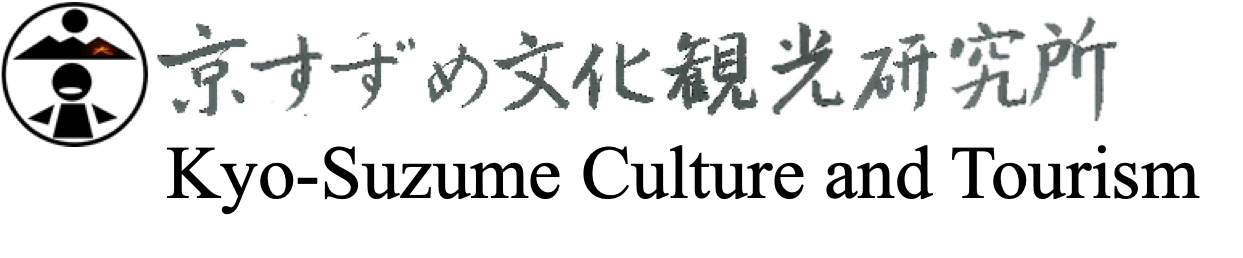京都の引力17 千年つづいた御所での祈り
土居好江

2020年5月23日撮影
京都御所見学会にて
京都市の真ん中にコンクリートではなく、砂利におおわれた京都御苑があります。この御苑に入ると、歴代の天皇が国家の安泰・平和と国民の幸せを祈られた祈りの願いが、土地の記憶として、現代の私たちにも何かオーラーのような気配を感じます。
御所は御苑の中の築地塀内の旧皇居を指します。御苑は御所を含む全体の敷地を言い、御所は天皇のお住まいを意味し、現在も天皇陛下、皇后陛下等が滞在されます。その御所のまわりにあった公家町が、現在では国民公園として開放されています。24時間、開放されていて、京都人の散歩コース、ランニングコースにもなっています。天皇が東京へ行かれて御苑の公家屋敷が荒れ果てたのを明治天皇がなげかれて、松を植え整備して国民公園として開放されました。この京都御苑は環境省の管轄で、御所は宮内庁、迎賓館は内閣府の管轄になります。京都御苑は日本で3つある国民公園で、京都御苑、新宿御苑、皇居外苑を指します。
延暦13年(794)から1074年間、京都が都として栄えた、こころの遺伝子が形づくられたのです。桓武天皇が平安京建都の折、風水地理学で都を定め一番良い処をお住まいにされました。つまり、比叡山の頂上、延暦寺から青龍がフゥーと息を吹き、一番良い気の溜まった処が千本丸太町だったのです。
そこが最初の天皇のお住まい京都御所です。いわゆる波動の良い場所を求めてお住まいを決められたのです。これはとても日本的な視点です。物質はすべて振動しており、波動を発しています。
平安京建都の理由
延暦13 年 (794) 10月辛酉 (かののとり) 22日、山城国葛野郡に平安京が建都されます。 「此の国は山河襟帯にして自然に城を作す。この形勝によりて、新号を制すべし。よろしく山背国を改めて、山城国となすべし。また、子来の民、謳歌の輩、異口同辞し、号して平安京という」 と 『日本記略』 の同年11月8日にあります。
(※辛酉の日とは革命の日とされていて、神武天皇の建国の時も同じ辛酉の日)
平安京が造営されて、大和からみて山の後ろ 「やまうしろ」 から転訛したと考えられる 「山城」 の命名は多くの示唆をもっています。日枝山 (ひえ) が比叡山になったと言われているように、夏至の朝日が都に差し込む位置にあるのです。
不思議なことに下賀茂神社の糺の森と、蚕の社の元糺と比叡山が夏至の日にライン上に並びます。
京都盆地の四隅に想像上の神、青龍、朱雀、白虎、玄武が都を守ると考えられていて、中国では紀元前から天地を往来する最強の神獣とされました。千年間、都であったまちは世界史的にみても珍しく、これが京都の誇る絶対差であります。
そこには王朝文化や雅な文化をつくりだした町衆の底力がありました。人間に記憶があるように、土地に記憶があるなら千年の都の記憶はピンチがチャンスの歴史であり、
栄枯盛衰を繰り返して不死鳥のように生き返ってきたまちが京都であります。
応仁の乱や明治維新というピンチの折、京都が生き延びた理由は何か。それは伝統産業と最先端技術をコラボさせて挑戦し続けた町衆の存在が挙げられます。1074年間、都だったエネルギーが満ちたまち・町衆の歴史があります。(つづく)
以上