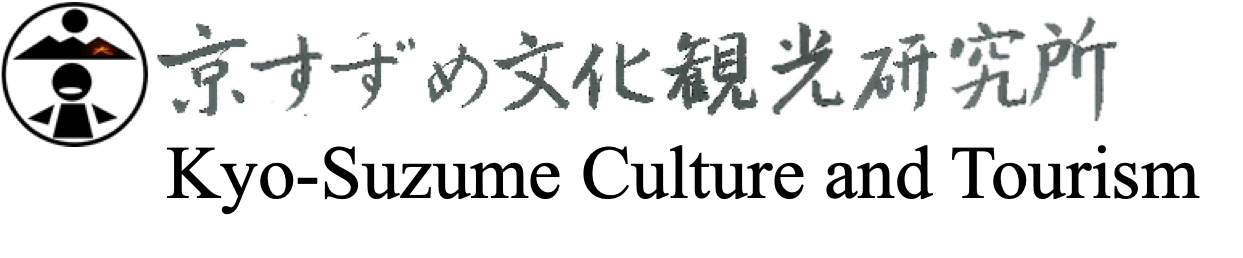京都の引力16 陶器と漬物Ⅲ 奈良漬
土居好江

奈良漬はキュウリ、スイカ、生姜の野菜を塩漬けにして、何度も新しい酒粕(さけかす)に漬け替えながらできた漬物のことで、もともとはウリの粕漬けからきていて、古代から食べられてきた漬物です。
醤(ひしお)と粕につけて野菜を保存した粕漬けを何故、奈良漬けというのか、という疑問は、平城京の長屋王邸から出土した木簡(現在の宅急便の配達票)に加須津毛瓜、(かすつけうり)加須津韓奈須比(かすづけかんなすび)、醤津毛苽(ひしおつけうり)等の記述があり奈良発祥の漬物らしいのです。平安時代の延喜式にも「粕漬瓜」があり、これが奈良漬の原型と考えられるようです。
奈良漬の記載がある古い文献は『山科家礼記』で、明応元年(1492年)に宇治土産として、奈良漬が記載されています。この時代以降、奈良漬が商品化され、普及していきます。特に奈良の漢方医の糸屋宗仙が白瓜を酒粕に漬け、奈良漬として販売します。
『浪華図絵』という書によると、徳川家康(1542~1616)は、大坂夏の陣で「あしひの杜」に陣を取った際、奈良名物として献上された奈良漬の味を、とても気に入ったと伝えられています。その後、天下を取り、江戸に戻ってからもその味が忘れられず、奈良から糸屋宗仙(いとや そうせん)という奈良漬作りの上手な医者を呼び寄せ、奈良漬作りの幕府御用商人にさせたというほど、お気に入りでした。
家康は医者も驚くほどの健康オタクで、薬草や漢方を自ら調合して、75歳まで生き伸びました。平均寿命30歳~40歳の時代のことですから、どれだけ長生きしたのかがわかります。
清酒技術の発展と共に、京都でも奈良漬が作られていきます。奈良には美味しい奈良酒があったそうですが、京都にも美味しい日本酒が沢山作られていました。もち米と米麹や焼酎などでじっくり熟成さて味醂を作りますが、この味醂で漬け込んでいるのが、田中長の奈良漬けで、1789年(寛政元年)の創業以来、自家製の奈良漬けを味醂に漬けこみ、2年間もの間、熟成させ、何回もの漬け替えを行いまろやかな味に仕上げます。創業以来200年間変わらない漬け方です。私も子供の頃から頂いている馴染みの味です。
奈良時代はドブロクの上澄みを酒として飲み、 下に溜まった沈殿物に塩漬野菜を漬けたものが保存食として貴重なものでした。当時の酒は現在とは異なり、白く濁ったドブロクです。粕とは搾り粕ではなく、どぶろくの底に溜まるドロッとした沈殿物の中に野菜を漬けこんだものを保存食としていました。当時の上流階級で珍重されていたようです。
奈良漬けと鰻の蒲焼きは、付け合わせにピッタリです。胃の働きを活発にしたり、胸焼けを抑えたり、脂肪の分解、ビタミンやミネラルの吸収を助ける効果がもあるようです。
うなぎの脂は酒精分の多い奈良漬と一緒に食べることで、口の中がさっぱりします。さらに、奈良漬には「メラノイジン」が含まれており、うなぎに含まれるビタミン・ミネラルの吸収を助けるはたらきも期待できます。この組み合わせは、明治時代から定番になりました。
以上