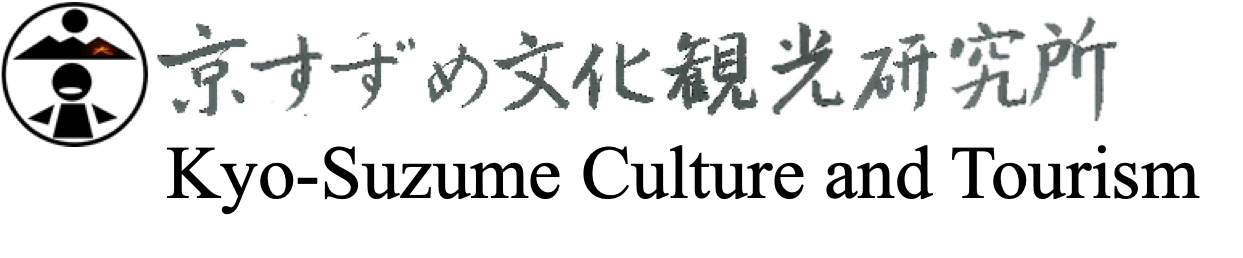京都の引力15 陶器と漬物Ⅱ すぐきと賀茂茄子、都野菜
土居好江
 |
 |
八隅農園すぐき小屋
12月になると、毎年、私は上賀茂の京野菜農家・八隅農園さんの「すぐき小屋」にすぐき漬を買いにお伺いします。すぐき小屋の10メートル手前ぐらいから、すぐき漬の良い香りが漂います。
すぐき漬の本漬けが終わると40度前後の室(むろ)で約1週間、乳酸発酵を促します。これが京都にとっては、冬の匂いであり味覚です。乳酸発酵しているので、胃腸の調子を整えるようで、便秘の方も快便になるようです。心当たりのある方は、お試しください。
すぐきの歴史は400年前、上賀茂神社の社家が賀茂の河原で見つけた植物を持ち帰ったことから始まります。江戸時代、元禄の頃に出版された『本朝食鑑』には『年を経て酸味を生ずるので酸茎と称す』と記されています。京都では明治の終わり頃、大阪・東京では大正時代から販売されています。すぐきの「天秤漬け」(天秤を使って漬ける)は、昭和初期からです。
江戸時代には秋から冬ではなく、初夏に上賀茂の特産品として、洛中の御所や公家、上層階級の人たちへの贈り物として重宝されます。すぐきは、その野菜の特性から漬物として用いられていきました。
御所から賜った植物を植えたのが始まりだという説もありますが、上賀茂神社の社家で栽培が始まったようです。社家の屋敷内で栽培されていたすぐきも江戸時代末期からは一般の農家でも作られるようになります。栽培地域が松ヶ崎より西、北山通りより北部という上賀茂の狭い地域に限られていたということもあり、門外不出の秘伝として栽培されました。一般的に普及しはじめたのは明治維新以降、明治末期になります。そして、すぐきは高級贈答品として定着していきます。
文化元年(1804年)に所司代から『就御書口上書』で、「すぐき」を他村へ持ち出すことが禁じられ、「すぐきはたとえ一本といえども他村へ持ち出すことを禁ず」と朱書きされており、栽培技術も種子も一粒たりとも持ち出されることがありませんでした。気候風土の問題もあり、この上賀茂の地だけに「すぐき」の貴重な発酵技術が現在に伝わることとなりました。
「すぐき漬け」に含まれている乳酸菌のなかでも、ラブレ菌」は「京都パストゥール研究所」の岸田網太郎博士により、すぐき漬けから発見されました。体内のインターフェロン(ガンやウィルスから身体を防御する因子)生産能力が高まり、安全で副作用のない免疫能力助長剤としての可能性があることが研究で明らかになり、このラブレ菌を使った漬物屋さんもあります。
以前、すぐきのことを伏見の京野菜農家さんにお聞きしていましたら、「すぐきのことは、上賀茂のすぐき農家さんに聞いて欲しい」と申されました。同じ京野菜農家でも、上賀茂のすぐきについては上賀茂の農家さんでないと、詳細がわからないとのことでした。
京野菜は、「京の伝統野菜」と「京のブランド産品」に分類されます。「京の伝統野菜」は、23品目が指定されていて、京都の風土で育まれた在来品種です。「京のブランド産品」は、京都府が独自に定めた基準を満たした農産物で、野菜だけでなく果物や米、加工品なども含まれます
他府県産の京野菜も数多く販売されている中、そこに疑問を持った「都野菜・賀茂」の東元大喜社長が、京都で京野菜を栽培した野菜を「都野菜」と命名しました。そして、朝採れの都野菜を店舗で畑バーとしてバイキングで提供されています。今や行列のできる野菜食べ放題の店となりました。大阪駅店ではNo-Foodloss Timeを、午後9時から状況に応じて実施され、顧客サービスが充実しています。京野菜への新しいチャレンジが、京野菜、都野菜の魅力発信に繋がっています。
この京と名前が付くのが曲者です。10年ほど前、パリへ行った時に行政機関を数軒表敬訪問して、興味深い話を聞きました。ヴェルサイユ宮殿の畑で京野菜を栽培して食事会をしたところ、賀茂茄子は大きくならず、茄子紺色に発色しなかったそうです。
これは京野菜というよりヴェルサイユ野菜でしょうか。賀茂茄子は繊細な品種で、伝統的な栽培技術と植える時期や実をつけるタイミングも難しく、伝統的栽培技術を駆使して京都の気候風土と土地でないと失敗することが多いのです。普通の茄子の3倍の水と3倍の肥料を使っても三分の一の収穫しかできない、お手間入りの品種です。
やはり京野菜の美味しさは、農家さんの愛情とお手間入りの作業の賜物で、気候風土、土の微生物や成分にあるのでしょうか。改めて京野菜の不思議さと美味しさに感動しています。 (次号へつづく)
以上