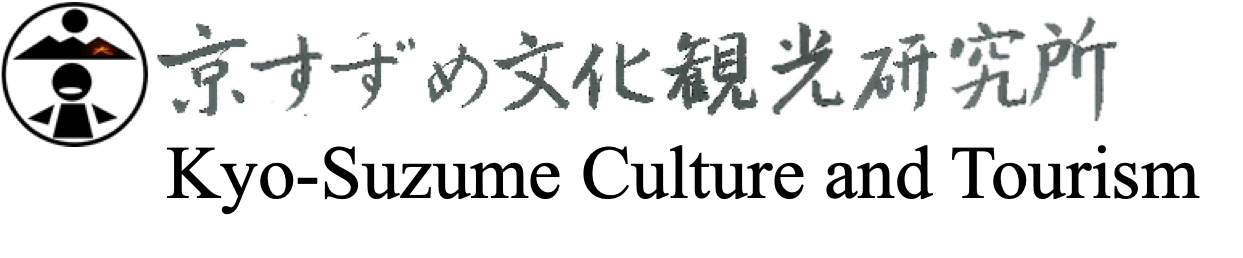かつらあめ
360年前創業の養老亭のかつらあめ、閉店12年後に復活!
甘蔦(あまづら)というぶどう科のツタの植物の樹液を煮詰めた蜂蜜のような黄金色 土居好江
 江戸時代から伝わる看板 |
 |
 桂女の衣装 |
 2025年5月5日に桂六斎念仏保存会 返礼品として、かつらあめが復活 |
 |
 松皮菱の紋様 |
桂女とは桂川で採れた鮎と桂飴を売り歩いていた女性のことで、平安時代から江戸時代まで桂に住んでいました。第12代飴屋利平衛こと遠山隆夫氏によると、江戸時代には、上桂に10軒、下桂に3軒あり、世襲制で現在は滅んでしまい、時代祭でのみ偲ことができます。桂女は衣装にも、桂飴の袋にも、女紋である松皮菱(まつかわびし)が描かれています。
『日本書紀』(720年)にはすでに「葛野」(かつらの)として桂が登場しています。「桂女」の特徴とされる、白い布で頭部を覆う「桂包」(かつらづつみ)は、神功皇后から「桂女」の始祖と言われる桂姫が頂戴した腹帯にルーツがあるとも言われています。何故、腹帯なのか、夫の仲哀天皇の急死後、身ごもったまま新羅征伐を行い、後の応神天皇の出産を遅らせる為に腹帯をしてお腹を冷やしたそうです。
「桂女」は、竹内宿禰の娘が「桂姫」と言い伝えられており、「桂姫」が伝えた飴の製法が、のちの「桂飴」となった伝説があります。また、平安時代後期には、桂川で収獲した鮎を朝廷に献上する鵜飼集団の女性が源流であるとも言い伝えられています。
桂飴の由来書には「元桂御所御所御飴所」と記されていて、桂離宮や宮家に献上してきた歴史があります。桂飴の第12代飴屋利平衛こと遠山隆夫氏によると、代替わり毎に、お代官に桂御所の御用の御飴商であることを文章にして提出していたそうです、店の入り口に菊の御紋の看板を掲げていました。
夏に食する氷の日本での氷を食べたという最古の記録は『枕草子』にあります。「あてなるもの」の段に「削り氷にあまづら 入れて、新しき金鋺(かなまり)に入れたる」という記述がそれです。また、時代が下ると、 氷室で冷やした菓子が持て囃されるようになり、それが形を買えて今日の京都名物・「みなつき」になっています。 これは現代風に訳せば「上品なもの。…細かく削った氷に甘いつゆをかけて、新しい金の椀に盛りつけたもの」ということです。京都にも氷室という地名がありますが、ここで、真夏に天皇に献上する氷が真冬から保存されていました。
平安時代には現在のような砂糖がなくて、甘蔦(あまづら)というぶどう科のツタの植物の樹液を煮詰めたシロップで、蜂蜜のような黄金色のものでした。これが桂飴の原料となってものです。応神天皇がご幼少の頃にミルク代わりに飲まれていたのが甘蔦の飴のお湯で溶いたものです。甘葛は砂糖が普及されると次第に忘れ去られてしまい、今では幻の甘味料となりました。当時は氷は貴重品でかき氷は貴族しか口にできないものでした。
以上