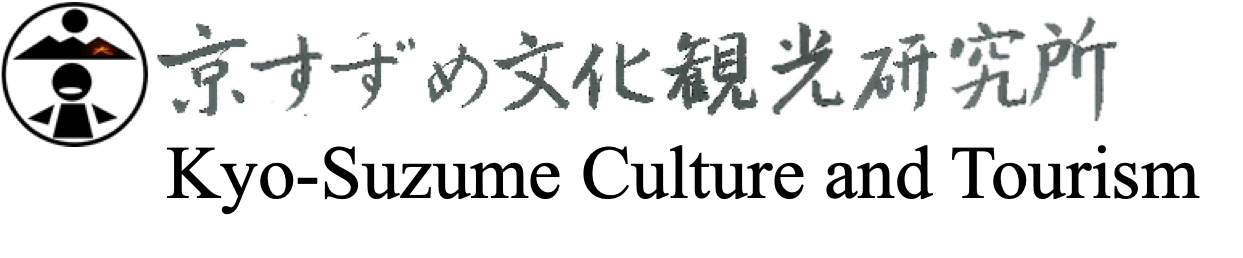京都の引力Ⅷ 祇園祭で何故、鱧を食するのか 中世の時代、女性で構成されていた六角町六角町生魚供御人 (ろっかくちょうなまうおくごにん)
土居好江
 |
 |
2025年7月8日撮影 六角堂
江戸時代末期まで祇園祭くじ取り式は六角堂で行われていた

六角堂境内にあるへそ石
7月に鱧を京都で食するルーツは江戸時代に遡ります。鱧は生命力が強く、水なしでも、浪速から京へ生き延びて運んでくることができました。江戸時代の錦市場の魚屋さんの絵図には沢山の魚が並んでいます。中世の絵図をみると、更に女性が魚商人として京の食文化を支えていたことがわかります。
中世の京都市内の魚といえば、鴨川、桂川、宇治川などでとれる鯉、鮒、鮎の淡水魚類が主な魚と思われがちですが、すでに六角町生魚商人が活躍していました。朝廷に所属する供御人の身分を持ちながら、六角町生魚供御人(ろっかくちょうなまうおくごにん)の活躍が文献から見受けられますが、この生魚商人が女性で構成されていたことが絵図(京洛月次風俗図扇面面流図屏風 光圓寺蔵)からわかります。女性の活躍が中世の京都で食文化をささえていたことは、とても嬉しいです。
2017年に発屈された六角町の遺跡からは、大量の魚、貝、鳥、小型哺乳類の骨などが、出土しました。ナマズ、鯉、から鱧、ニシン、ボラ、ハタ、ブリ、キダイ、クロダイ、マダイ、アマダイ、タヌキ、ウシ、鹿、野ウサギ、クマ、ネズミ、キジ、サギ、ツル、カモなども出土しています。
これは遠くの港から干物や塩合ものだけでなく、中世から京都市内で海産物が食されてきたことがわかります。
祇園祭のある時には八坂神社の裁量で鱧が京都でも買えるようになったのが、祇園祭の月だったようです。鮮魚を運搬するのが難しい時代、鱧は生命力が強く、水なしでも、浪速から京へ生きたまま運んでくることができました。梅雨の水を飲んで、美味しくなるといわれる鱧の旬と重なり、鱧料理が定着しました。
鱧の語源は食む(はむ)だそうです。鋭い歯で何にでも食らいつく、どう猛で生命力が強い魚です。鱧は他府県では出汁に取ったあとは、すてられる魚でした。京都では鱧の骨切ができて一人前の料理人であると言われるように、捨てるような魚を美味しく調理して頂きます。
鱧料理は鱧のおとし(湯引き)・鱧の造り・鱧の葛だき・鱧しゃぶ・鱧寿司・焼き鱧・揚げ鱧等で、おもてなしをしたことから鱧祭りとも言われるようになったようです。
鱧は東京・築地市場と比較すると京都で約10倍の取引量(年間1,000トン前後)があるとも言われ、初夏から秋に掛けての取引量が全国トップになるようです。
特に祇園祭の宵山(前祭)が行われる7月14日から16日頃から急増し、山鉾巡行(前祭)・神幸祭が行われる7月17日頃にピークを迎え、1日10トン近く取引されることもありました。
どういう訳か、江戸時代、熊本県(細川藩)の料理人が鱧の料理して提供していました。京都が鱧料理の本場ですが、江戸時代から熊本の料理人と京都の料理人が交流していたのではないかとも伝えられていますが、確たる証拠はありません。
鱧は小骨が多く、鱧を美味しく食べる為に1センチに7、8回切り目を入れる骨きりが生まれました。1寸、(約3㎝)24に切り目を入れるのです。鱧には骨きり専用のハモ骨切り包丁も存在します。皮一枚を残して身と骨だけに刀を入れる職人技です。
京都では鱧の骨切ができて一人前の料理人であると言われるように、捨てるような魚を美味しく調理できて一人前と言われています。
鱧料理店のご当主にお話をお聞きすると、鱧は秋が美味しいのだそうですが、京都では祇園祭の時期に一番多く食されます。
江戸時代の錦市場の魚屋さんの絵図に鱧が並んでいます。祇園祭の7月には八坂神社の裁量で鱧が京都でも買えたのです。それで、夏に鱧を食するようになったとも言い伝えられています。
魚の保存方法にも、京都の清涼な地下水を利用した天然の冷蔵庫が活躍しました。(次号へつづく)
以上