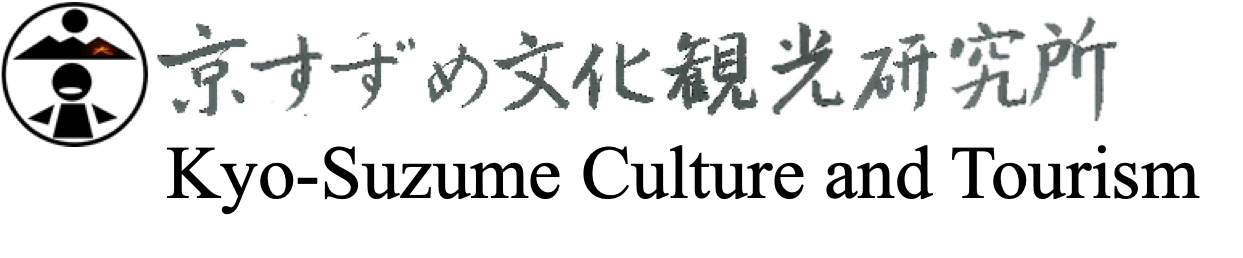『京都火(灯)物語 』講座
動物と人間との差は遺伝子レベルでは、それほど変わらないとされていますが、決定的な差は人間は火をつかうことが出来ます。人類が火を使ったのは、約30万年前、北京原人とされています。日本でも8000年前頃、縄文時代以前の遺稿に焚き火跡と炭灰が発見されて、火の存在が証明されています。
火は暖房と照明、調理、金属生産、焼畑、漆、陶磁器、ガラスの製造、養蚕、除虫、まで、あらゆる分野で利用されます。それと同時に火の持つ神聖さは神事でも火の持つ力で神や先祖を迎えたり、見送ったりしています。京都では“おけら参り”で1年が始まり夏の五山送り火や鞍馬の火祭など、暮らし煮寝根付いた行事も多く見受けられます。
火と暮らしの関わりの中から、ガスや電気のライフラインで便利になった今、忘れられている火の意味を改めて考えてみたいと思います。
暮らしの中で火(灯)の持つ意味を考え、火の文化を探るカリキュラムとなっています。
主催;遊悠舎京すずめ
文化庁関西元気文化圏参加事業
(京すずめ京都通認定評価対象講座)
第1回 江戸時代から変わらぬ製法でつくる和蝋燭
 |
講座概要
|
~蝋燭の文化史~
江戸時代から変わらぬ製法でつくる和蝋燭
講師: 丹治蓮生堂 店主 丹治潔氏 |
|---|---|---|
|
日時
|
2007年4月22日(日)午後1時~3時30分
|
|
|
場所
|
丹治蓮生堂、西本願寺 聞法会館
|
第2回 行灯・提灯から電灯
 |
講座概要
|
行灯・提灯から電灯
講師: 高橋提灯(株)代表取締役 高橋康二氏(工房見学と講演)
|
|---|---|---|
|
日時
|
2007年5月26日(土) 午後1時30分
|
|
|
場所
|
高橋提灯(株)工房
|
第3回 おくどさんの文化史
 |
講座概要
|
おくどさんの文化史
講師: 地生きネット京都 吉田好弘氏
|
|---|---|---|
|
日時
|
2007年6月29日(土)午後1時30分~3時
|
|
|
場所
|
四条京町家(京都市伝統産業振興館)
|
第4回 1200年伝教大師から続く不滅の法灯
 |
講座概要
|
1200年伝教大師から続く不滅の法灯
講師: 延暦寺・大林院 住職 今出川行雲先生 |
|---|---|---|
|
日時
|
2007年11月18日(日) 午前10時
|
|
|
場所
|
延暦寺・大書院
|
第5回 おくどさん」炊飯体験講座
 |
講座概要
|
「おくどさん」炊飯体験講座
(第41回京すずめ学校 京都火(灯)物語)
|
|---|---|---|
|
日時
|
2008年3月9日
|
|
|
場所
|
京都上桂「苔香居」
|
Please feel free to contact us070-6500-4164Reception time 10: 00-17: 00 [except Saturdays,Sundays,and holidays]
Contact Us Please feel free to contact us