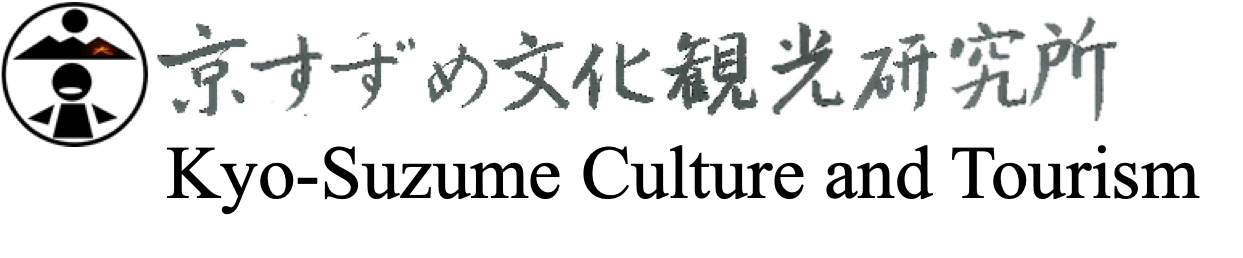近畿農政局 関西 食の「わ」マルシェ 読売新聞大阪本社でのセミナー終了のご報告
土居好江
 |
 |
 |
近畿農政局 関西 食の「わ」マルシェ会場
2025年4月22日読売新聞大阪本社の1階ロビーで、近畿農政局 関西 食の「わ」マルシェが開催され、京すずめでは、セミナーを2回担当させて頂きました。おくどさん未来衆代表の長谷川検一氏(あぶり餅一和当主)と同じく未来衆の宮奥淳司氏(宮奥左官工業所)同じく未来衆の炊飯名人飯兵衛こと武本秀明氏、そして土居好江、大谷正美の5名でリレー式にプレゼンをさせて頂きました。
お一人おひとりの方のお話をお聞きしたことは何回もあるのですが、リレー形式でプレゼンテーションを行ったのは初めてのことでした。
最初に土居からは、「電気ガスの時代に何故、おくどさんをつかうのか?」というお話をさせて頂きました。その理由はご飯が美味しいからです。瑞穂の国の日本人でありながら、本来の美味しいご飯を召し上がって欲しいとの想いからおくどさんサミットを開催し、おくどさん文化の継承をしています。また、自然の循環システムがおくどさんにはあります。そして、家族の団らんがおくどさんを中心にしてあったこと、伝統的価値観のおくどさは最先端の科学との懸け橋となる存在であり、火の文化こそ、人類を進化させてきた文化だとお話させて頂きました。
更におくどさんを現在も使用されている店舗やご自宅も写真でご紹介して、おくどさんサミット、おくどさん未来衆会議についてもご紹介させて頂きました。
長保2年(1000年)創業のあぶり餅一和のご当主・長谷川検一氏は世界最古の現存する飲食店として、千年以上も同じ井戸水が湧き出で、おくどさんを使い、同じ製法で作り続けているお店の哲学を通して、ご先祖様が大切にされてきた井戸やおくどさんを守り、当家の起源として伝えられる創業時期の長保2年(1000)は、今宮社の創祀時期であり、あぶり餅の起源として船岡山の西北麓側にあったとされる香隆寺(現在は存在しない)、の名物であった、おかちん(「餅」の貴族女房ことばである「かちいい」から派生した言葉;「かち」とは餅をつくという意味で、「いい」とは飯でもち米のこと)を疫神にそなえたものとの口伝もこの起源につながると話され、現在においても今宮祭の神輿には一和で蒸したもち米を神饌として供える習わしが続いているとのこと、歴史を感じるお話でした。
おくどさんをつくる宮奥淳司氏からはおくどさんをつくる過程の動画を、皆様にご覧頂きながら、自然の土、藁を発酵させてつくるおくどさんが如何に自然界の法則にあっている法則なのかをお話頂きました。現場で実際におくどさんを作ったり、修復したりされている貴重なお話でした。おくどさん文化の継承のキーワードのお話でした。
次に美味しいご飯の炊き方を武本秀明さんからお話をして頂きました。伝統的な炊き方と災害時でのおくどさんの役割等いついてお話をされ、最後に大谷正美氏から、商標や京都への恋文について、説明がありました。
以上